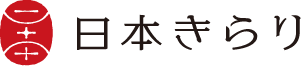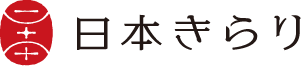気仙沼の復興はフカヒレ抜きではありえない。
地元の人々と手を取り合いながら、
フカヒレ文化の伝承に人生を捧げる覚悟です。
石渡商店
石渡久師さん(宮城県気仙沼市)
サメの水揚げ日本一を誇る気仙沼で、世界に冠たる高品質のフカヒレを生産してきた石渡商店。東日本大震災で壊滅的な被害を受けながらも、技術と人材は失っていないと、力強く立ち上がった若きリーダー。
会社の再建、そして故郷・気仙沼の復興に向けて、石渡久師さんのチャレンジは始まっている。
変わり果てた故郷で目にした、石渡商店の看板
三陸沖の豊かな漁場に恵まれ、古くから日本有数の漁港として賑わった気仙沼。港から見渡す気仙沼湾は、リアス式海岸独特の美しさと穏やかさを湛え、どこまでも碧く輝いている。かつて、この海を絶え間なく行き来した大小の漁船。港に響き渡る水揚げ作業やセリの掛け声。休日には多くの観光客も訪れ、新鮮な魚介をはじめとする土地のグルメを楽しんだ。
そんな活気にあふれる港町の日常が失われてから1年。地震と大津波に加え、夜通し続いた火災、そして大規模な地盤沈下が発生した気仙沼では、未だに瓦礫の撤去作業が続けられていた。多くの建物が消えて荒野のような風景が広がるかつての市街地には、打ち上げられた大型漁船や、ねじ曲がり焼け焦げた歩道橋、建物の半分をえぐり取られたままたたずむ家屋や工場跡が点在し、今なお被害の甚大さを生々しく伝えている。この一年、繰り返し言われてきた「被災地の復旧・復興」が、想像よりも遥かに長く険しい道のりであることを、改めて思い知らされる。
「被災した町を最初に目にした時、あまりの非現実的な光景に何も感じることができませんでした」
そう当時を振り返る石渡商店専務取締役の石渡久師さん。震災当日、久師さんは中国の上海に出張中で、街中の巨大モニターで津波に襲われる故郷の映像を茫然と見つめたという。気仙沼には妻と幼い娘二人を残してきている。翌日、成田に到着してからは友人のバイクに乗って北を目指すも今度は福島の原発で爆発事故が発生。絶望的な状況の中、最後は偶然目にした自動車整備工場に頼み込んで車を借り、20時間以上をかけてようやく気仙沼にたどり着くことができたという。高台にある祖母宅で家族全員の無事を確認し、不安に苦しめられた長く過酷な状況にホッと一息。久師さんが変わり果てた故郷の町を見つめたのは、そんな経験をした直後だった。
「まるで夢を見ているようでしたが、流されたと覚悟していた自宅兼工場にたどり着いた時、崩れかかった建物の上に“ふかひれ石渡商店”の看板が見えたんです。そこで一気に悲しみがこみ上げてきました」
石渡商店の創業は昭和32年。久師さんの祖父である石渡正男さんが、それまで研究員として働いていた大手食品会社を退職し、家族ともども神奈川県から気仙沼へ移住して、乾燥フカヒレの製造、香港などへの輸出といった事業をスタートさせた。
正男さんは持ち前の研究熱心さで、旧来の常識にとらわれない新しい製法や技術を次々に考案していった。なかでも生のヒレから余計な皮や骨、肉を取り除いた「素むき」は、石渡商店が開発し、今では世界共通の業界用語となった製法だ。
当時フカヒレと言えば生のヒレをそのまま乾燥させた「原ビレ」で取引されるのが一般的で、以降の処理は料理人の仕事であった。また、江戸時代に乾燥フカヒレは中国との貿易において「金銀銅」の代わりに決算ができる「乾貨」として扱われた歴史があり、伝統的にサイズや重量が価値として重視される傾向にあった。そのような業界の習慣があるなかで、手間がかかる上に、サイズや重量も目減りしてしまう「素むき」にあえて取り組んだのは、「その方が美味しくなる」というシンプルかつ真っ当な理由からだった。
食べ物をより美味しく味わうことで、限りある海の幸を大切に想う心を育て、豊かな食文化を創造する。初代から現社長である2代目、石渡正師さんに貫かれるその信念のもと、新しい取り組みにチャレンジし続けてきた石渡商店のフカヒレは内外から高く評価され、中国からの来賓を迎える政府の晩餐会や、天皇即位を祝う宮中晩餐会に使用されるなど、気仙沼を代表するフカヒレ専門店へと成長を遂げてきた。
そんなフカヒレ一家の3代目として、ここ気仙沼に生まれ育った石渡久師さん。学生時代は陸上競技に打ち込み、将来は体育教師を目指した時期もあったが、やがて家業を継ぐことを決意。平成14年の入社からおよそ10年、父のもとでフカヒレのすべてを一から学んだ。近年は景気の悪化で高級食材であるフカヒレの国内需要が落ち込んでいたが、代々受け継がれるチャレンジ精神を発揮し、本場中国での販路開拓に取り組んでいた。大震災が起こったのはまさにその出張中。いくつかの料理店と取引の話が進み、さあこれからという矢先の出来事だった。